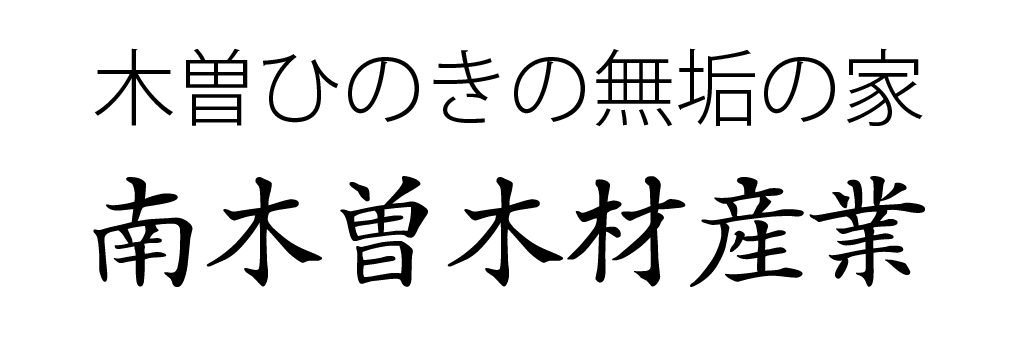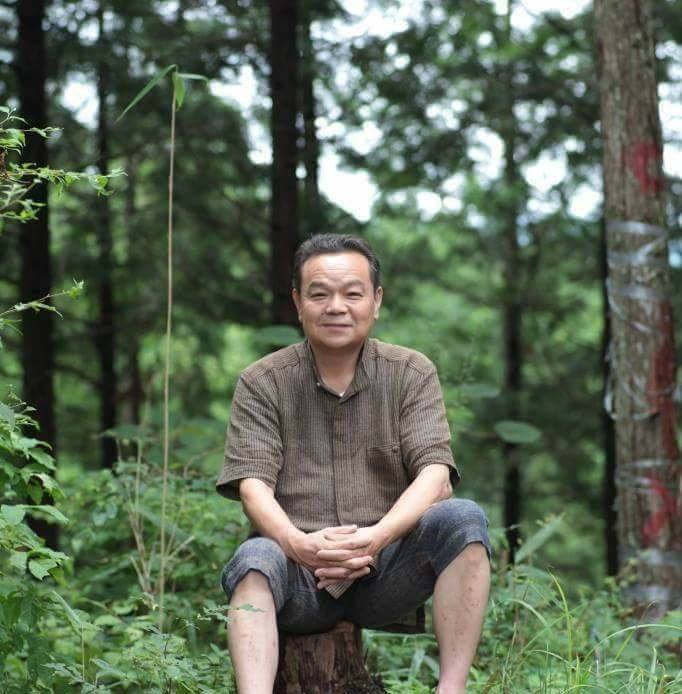誰もが知っているように、木は二酸化炭素を吸収してくれます。それが、地球環境を維持する大きな源になっています。でも、森を増やして木を伸ばし放題にしておけばよいかというと、そうではありません。
木は若いうちはたくさん光合成を行い、葉を茂らせ、幹を太らせていきます。しかし、一定の年数を経過すると、炭素の吸収力が減少します。よって、計画的に植林と伐採を繰り返して、新しい若木を育てることが重要になります。伐採した木が売れれば、そのお金で植林するための経費に充てることができます。でも、残念なが、今の日本では、「安い」というそれだけの理由で、外国からの輸入材が使われています。日本の森は、木材が売れないためにお金や手間がかけられず、たいへん荒廃しています。

南木曽木材産業 本社にて
発展途上国の違法伐採
違法伐採
一部の発展途上国では、輸出のために森が無計画に伐採されています。インドネシアでは産出木材の五割が違法伐採だという調査結果が出ていますし、ロシア極東(シベリア)地区でも違法伐採材が相当の割合を占めていると言われています。
地球規模の環境破壊とあるこれらの問題に対して、国際会議における協議や、NGOによる監視、さらに森林認証制度の導入(後述)などの対策がなされていますが、木材は伐ってしまうと出所がわからないため現行犯逮捕に頼らざるを得ず、また途上国は外貨獲得を木材に頼る部分が大きいため消極的な姿勢を取るなど、解決は容易ではありません。

日本の立場と役割

日本や中国などの木材輸入大国が、この環境破壊を促進している面は大いにあります。近年、製紙会社など木材輸入の大手には、外国での植林を行ない、そこから輸入するなどの対策を採っているところも出てきました。しかし、大半は安値であれば出所を問わず購入する状態にありますし、問題になっている地域のものでも、第三国を経て出所がうやむやにされ輸入されている木材も多くあるといわれています。地球温暖化対策の国際的な高まりの中で、今後の木材貿易は、様々な規制が掛けられていくことになるでしょう。そのためにも、木材自給率を高めることは緊急の課題です。
「参考資料:日本の木で家を建てよう 菅野知之著 春秋社」